労働安全衛生
安全対策
採用時の従業員への安全教育
過去に発生した労災を基に「雇入れ時の安全衛生教育実施シート」を作成し、各拠点毎に採用時の従業員への安全教育を行なっています。
電動工具についての
注意喚起
電動工具などの使い方について毎月発信し、労災の防止に取り組んでいます。
材料固定をしっかり行う
-

材料が回転して危険!手の力は回転工具にはかないません。
-
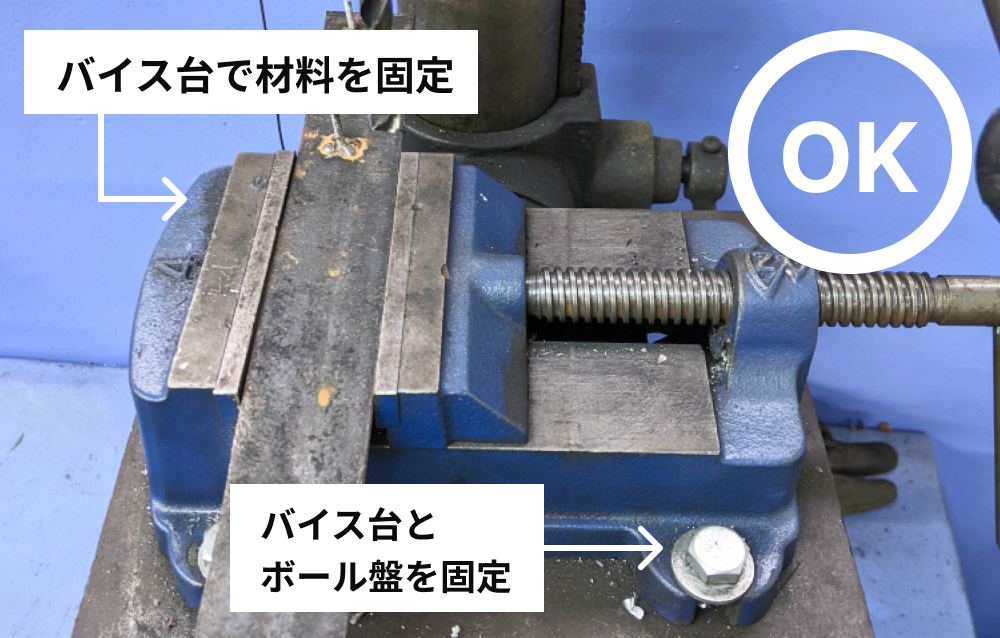
安全かつ高い加工精度
工具の点検を行う
-

ホイールカバーが緩んでいませんか?
-

外観にひび割れが発生していませんか?
コードに気をつける
-

コードが回転部付近にありませんか?火花が飛ぶ位置にありませんか?
-
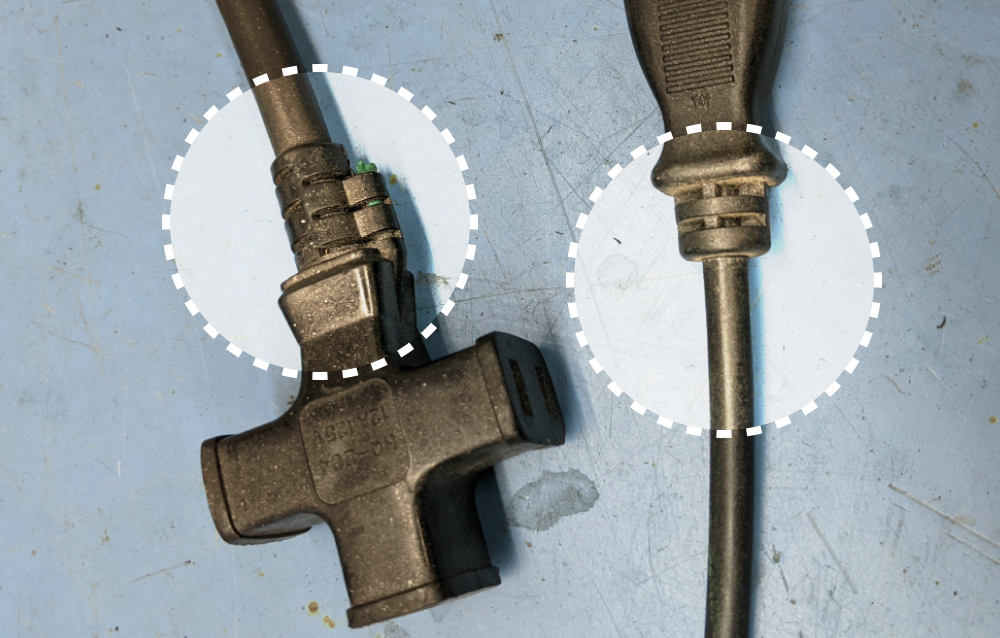
被覆がやぶれていませんか?
つぶれた痕跡はありませんか?熱を持っていませんか?
危険箇所の見える化
拠点内の危険箇所を可視化し注意喚起をおこなうことで、労災の防止に取り組んでいます。
-

足元注意!
サイドスリップテスターは未使用時はロックを掛ける。上を通行しない。 -

頭上注意!
分解整備作業場の階段下辺りで作業する場合は、頭上に注意する。 -

落下注意!
高所作業時はヘルメット及び安全帯を着用する。
衛生対策
-
ストレスチェック実施
働きやすい職場環境を構築し、メンタルヘルス不調を“未然”に防止するため、毎年1回ストレスチェックを実施しています。
-
健診の費用補助の充実
特定のがん検診や人間ドックの費用の一部を補助
女性向けに子宮頸がん検診、乳がん検診。男性向けにPSA検査(前立腺がん健診)。また人間ドック受診時にそれぞれ補助金が設定されています。大腸がん検診、ピロリ菌検査も受検できます。 -
健保との連携による
健康保持増進の取り組み肥満者への特定保健指導、禁煙推進。健保HP「MY KENPO」上で指定の健康増進行動をとることでポイントがたまり、商品と交換できるヘルスケアポイントなど、健康保持増進に取り組んでいます。
年間計画
- 月度
- 労働災害防止
- 健康衛生関連
- 4月度
- 5月度
- 6月度
- 7月度
- 8月度
- 9月度
- 10月度
- 11月度
- 12月度
- 1月度
- 2月度
- 3月度
労働災害防止
労働安全衛生に関する指針表明
雇入時の安全衛生教育
労働者代表の選出について
健康衛生関連
腰痛予防の推進
健康診断受診についての順守事項(健康診断に向けて)
労働災害防止
過去の労災による指導教育
安全な電動工具の使い方11か条①
ストレスチェック実施における審議事項
健康衛生関連
食中毒の予防(発生が増え始めるため)
生活習慣病(肥満)予防の推進
労働災害防止
化学物質に関するリスクアセスメントの実施
安全な電動工具の使い方11か条➁
全国安全週間準備期間
健康衛生関連
熱中症予防の推進
健康診断有所見者の管理と指導
禁煙促進および受動喫煙の防止
労働災害防止
安全な電動工具の使い方11か条➂
全国安全週間
若年層向け労災防止教育の実施
健康衛生関連
熱中症予防の推進
質の良い睡眠の取得推進(寝苦しくなる時季)
健康診断再検査者の管理と指導
労働災害防止
ヒヤリハットに基づく指導(構内リスクアセスメントの準備)
安全な電動工具の使い方11か条➃
健康衛生関連
熱中症予防の推進
健康診断有所見・再検査者の管理と指導
労働災害防止
安全な電動工具の使い方11か条⑤
全国労働衛生週間準備期間
構内のリスクアセスメントの実施
健康衛生関連
熱中症予防の推進
健康診断有所見・再検査者の管理と指導
労働災害防止
全国労働衛生週間
安全な電動工具の使い方11か条⑥
健康衛生関連
食中毒の予防(発生が一番多い)
がん予防の推進(乳がんピンクリボン10/1~10/30)
労働災害防止
安全な電動工具の使い方11か条⑦
構内のリスクアセスメントの実施
健康衛生関連
腰痛予防の推進
長時間労働等による脳・心臓疾患予防の推進
感染症予防の推進(インフルエンザの予防接種対象)
労働災害防止
年末年始無災害運動
安全な電動工具の使い方11か条⑧
化学物質に関するリスクアセスメントの検証
健康衛生関連
健康ダイヤル24の活用
労働災害防止
年末年始無災害運動【継続】
安全な電動工具の使い方11か条⑨
健康衛生関連
高血圧予防の推進
労働災害防止
安全な電動工具の使い方11か条⑩
健康衛生関連
朝食の重要性(食育の推進)
労働災害防止
フォークリフトの総点検
安全な電動工具の使い方11か条⑪
健康衛生関連
働く世代の健康課題
ハラスメント対策

また、年2回、ハラスメント防止月間を設けるなど、定期的な教育を実施しています。


